No.130 トランプ関税と純粋まっすぐ君
- トランプ氏が当選したのが2024/11/6で就任式が2025/1/20。就任するやいなや、大統領を山のように発令し、バイデン政権、民主党政権のやってきたことを全否定して、署名したボールペンを聴衆に投げてプレゼントする姿は、不謹慎だが気持ち良いほどのパフォーマンスだった。まことに彼は「見せること」に長けている。某国のモゴモゴ何を話しているか、わからない政治家には見習ってほしい。リーダーは「こっちで行く!」と決めたら、それをはっきりと示すのがミッションだ。


- ところがあれから2ヶ月強しか経っていない現在、彼への意見・批判・メディアの取り上げる量は半端ではない。言うまでもなく「トランプ関税」の発表だ。「ほとんどの輸入品に対して、一律10%の関税」に加え、中国への追加関税25%(やがて125%!)、そして他の国も相互関税を課し、その時の会見で出した青と黄色のフリップの内容はなかなか強烈だった。特に相互関税を決めた根拠として出された、「各国が米国に如何に不当な関税をかけているか」という青色の部分はシビレる。中国67%、欧州39%、ベトナム90%、台湾64%、日本46%,,,最初の数行を見て、「え、マジっすか?」と呟いた人も多いだろう。で、「でも、日本は良いヤツだから、我が国からむしろってイル46%の半値の24%に相互関係はおまけしてやるよ」と。あのねえ、バナナのたたき売りじゃないんだからさ(苦笑)。
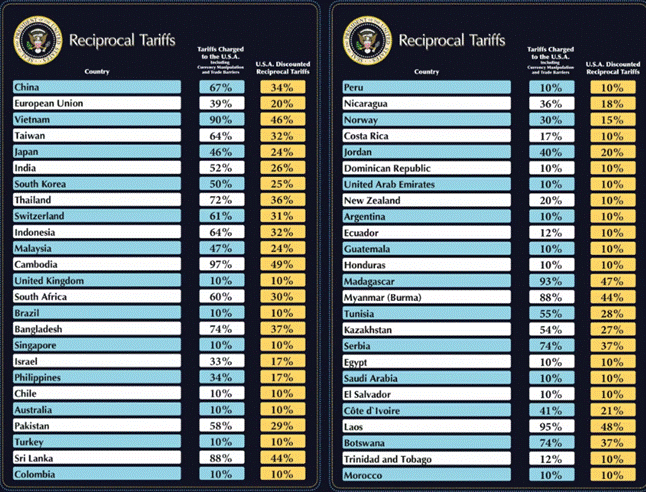
- で、さすがエコノミストとか国際経済学者というのは凄くて、この青色部分の算式が如何にでたらめなものかを暴いたのは、わずか4-5日後だった。ご存じの通り、「各国に対する貿易赤字額÷米国の輸入額」を割っただけだ。しかも、完全を化した場合の輸入価格の変動係数と、輸入価格に対する輸入需要の弾性値という「いかにも、俺たちは考えているのだよ」という変数をぶっ込んでいるのだけど、前者は0.25で後者は4だから結局1になる。米アメリカン・エンタープライズ研究所がここを調整して、関税を計算したのが下表であり、「あら、ま、びっくり」だ。
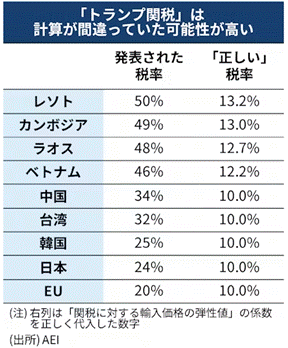
- で、トランプ氏の真骨頂は続く。まず、中国政府がただちに「不満である」と表面した途端、それまでの34%の関税が125%に。一方、関税は輸出国が支払うのではなく、輸入する米国の消費者が払うという「当たり前」のことが米国内で市民に広まり、市民の反トランプ運動が強くなり、4/10には相互関税を90日間停止すると発表した。つまりは、猶予を与えるから、交渉しに来いということだろう。この朝令暮改も凄いけど、そのことになんの痛痒も感じていない彼のキャラクターも凄い。そして、その間でも「iPhoneは米国内で作れる」とか「自動車も米国内で製造できる」(トランプ氏よりもナバロ氏の発言がなかなか凄かった)などと発言しまくるのだけど、高校生でもわかるように複雑な工業製品はもはや部品(パーツ)を世界分業で製造しており、米国が鎖国状態になってしまったら、部品がない以上、アッセンブリした完成品は作れない。下表は「デトロイトが米国製造に最も貢献している」というグラフなんだが、部品はカウントされてない。これをうけ、4/2のブルームバーグは既に「米政権がのぞむ米国製自動車、定義は複雑怪奇」というコラムを書いている。

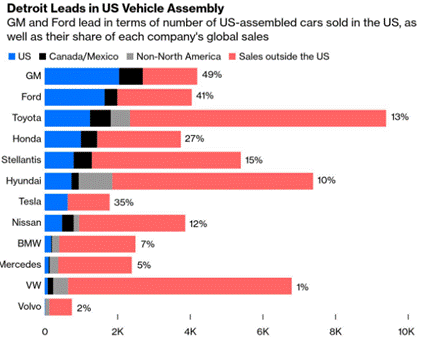
- そして言うまでもなく、このコロコロと変わる発言と、信頼性の薄いバックデータに振り回されて高いボラティリティを記録しているのが金融市場だ。下はすべて六ヶ月での米国ダウジョーンズ、日経225平均、円ドルレートのグラフだが、相当な変動だ。日経新聞の4/9の記事によれば、トランプ関税の騒ぎで世界の株式時価は1割(=12兆ドル、1,800兆円)消失したそうだ。世界中の投資家もそうだが、「貯蓄から投資へ」がやっと浸透し始めた日本の当局は気が気ではないだろう。

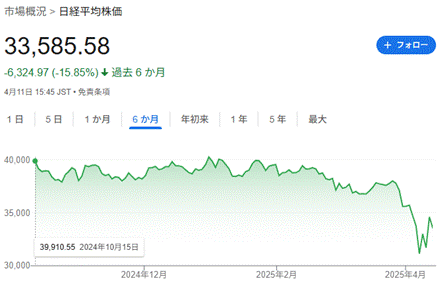

- 多分、この状況だと当面は市場のボラティリティは高く、方向性は一定には向かわないだろう。円高になるのは物価低下要素で嬉しいけれども、外貨建て資産としてはマイナスなので、痛し痒しだ。で、それを受けて、SNS、特に金融系のSNSを読むと「新NISAを即刻解約します!」とか「iDeCoをやめなければ」とか、「日経平均3,000円を予測した故・森永卓郎さんは正しかった」など、色々な書き込みが読めて面白い。いや、お金を損している人を前にして「面白い」というのは失礼だろうが、でも、やっぱり面白い、というか、可笑しい。
- 言うまでもなく、まず積立NISAをしている人にとっては、ドルコスト平均法で毎月購入しているから、インデックスが下がれば安く多く買えることになる。筆者のように余命がさほどない人間は別だが、20代、30代の方々にとって影響はフラットだ。積立していなくても、余剰資金があるならば、ここまで暴落した段階で、ちょっと試しにナンピン買いをしてみるのは悪い話ではない。厳しいのは筆者のように投信を購入してしまった人間だが、先行き不透明ということはどうなるかわからないのだから、一番良いのは動かないことである。失われた30年で日本市場の株価はとことん下がったが、それが昨年、その最安値を超えたのは事実だ。問題は時間軸だけである。
- それよりも気になるのは、こういう事態になると「トランプ氏は大統領として相応しくなかった」だの「彼は経済のことを全くわかっていない」だのと騒ぎ、しかし、結局は確たる予測が出来ない野次馬が多いことだ。漫画家の小林よしのりさんは、色々な視野をもたずにただひたすらに思い込みで批判したりするむきを「純粋まっすぐ君」と揶揄的に呼んだが、筆者も正直、これほど「純粋まっすぐ君」が多かったとは思わなかった。ま、小林さんも思い込みの激しい人であり、彼自身が「純粋まっすぐ君」であるというアイロニーも存在するのだけど。


- 唐突だが、筆者は高校生の頃、バンドを組んでいた。で、バンドメンバー三名とも、どうやら現役での大学郷学はほぼ100%無理とわかり、「高校時代の思い出になることがしたい」と受験勉強からの逃避もあって、ラストライブをやらせてくれるように教員に掛け合ったことがある。とはいえ、卒業してからのラストライブ@高校の講堂、である。教員にしてみれば、卒業した人間が学校の施設を利用するのは危機管理から考えても躊躇したのだろう。ガンとして良い返事はくれなかった。
- それで、我らがバンドリーダー(=今は新宿歌舞伎町でバーのマスターしてます)は校長先生に直談判に行った。意気揚々と向かった彼だったが、一時間後、その意気消沈左派痛々しかった。彼はこう言われたそうだ、「××君、君たちだけがものを考えて生きているわけじゃないんだよ。教員や事務の人達も色々なことを考えて判断し、生きていかなければならない。高校を卒業したならば、そのことを理解しなさい」。リーダーはぐうの音もでなかったそうだ。
- なんで、こんな思い出話をするかと言えば、世間一杯にマスメディアやSNSなどで政治家や高い地位を持っている人は、まるで阿呆のように批判されるのだけど、常識的に考えても、彼らに集まってくる情報量と考えている思考プロセスの複雑さは、私どころの比ではない高度で精緻なものだろう。そりゃ、キャラクター的にどうよ、という人はいるけれども。筆者には、トランプ氏が今回、世間で言われるほど無能で、無知で、阿呆のようにはおおよそ思えないのだ。なんといっても、何度も倒産を経験し、それで爪を剥がして地獄の底から這い上がって来た人物だ。その経験値は半端ではないだろうし、ビジネスマン出身の彼が得意とするのは「交渉(=ディール)」だろう。それは、最初は高い値段をつけておいて、交渉しながら、値段を下げて上げつつ、ほかの条件を付与してトータルでメリットを得ようとする私たちの仕事となんら変わらない。それを世界滅亡のように批判し、叩くのはどうなのかしらんと筆者は思ってしまうのだ。

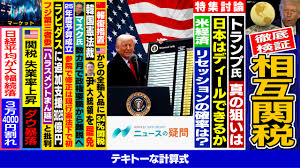
- ただ、ひとつだけ言えるのは、やはりマネー、市場は正直だということだ。トランプ関税による騒動で、米国債が売却され、10年先物金利が4.49%まで上昇した。識者によれば、9.11依頼の上昇幅だという。言うまでも無く、ドルが基軸通貨であり、いまなおドル建て決済を輸出入業者が望むのは、なんだかんだ行っても米国債は「安全資産」であるからだ。しかし、今回の騒ぎはその常識に水を差すこととなった。米国債が売却され、米国から資金が逃げ出せば、これまでの常識はいとも簡単に瓦解する。ちなみに、2024年3月時点の米国債を保有している国は、一位日本(1兆1,778億ドル)、二位中国(7,750億ドル)、三位英国(7,234億ドル)である。日本が同盟国である米国にケンカを売って、米国債を前売却するということはないが、しかし、米国側がそのリスクを考えていないわけではないだろう。実際に売らなくても、「米国債がリスク資産化することは好ましいことでは無い」と日本側が発言するだけで、ボラタイルな金融市場はさらに荒れるだろう。この点だけは、日々、注意しておきたい。

(了)
[補足1 自己紹介]
- 佐々木泰行事務所・代表研究主幹の佐々木泰行です。
- 1988年に野村総合研究所に入社以降、証券アナリスト・研究員をして参りました。メリルリンチ証券、クレディスイス証券、リーマンブラザーズ証券で多くの方にお世話になったのですが、2008年のリーマンブラザース破綻による野村證券移籍以降は投資銀行業務のリサーチャーを致しました。
- 2020年に野村證券を円満退社し、4年ほど早稲田大学商学学術院で教員(研究院准教授)をしておりましたが、折悪しくコロナ禍で対面での調査研究が難しく、還暦を機に再び「一人証券アナリスト」というべき仕事をしております。そのため、流通・消費産業の調査歴は30年を超え、大変多くの方にお世話になったこと感謝しております。
- 現在は、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社( https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/dtfa/deloitte-tohmatsu-financial-advisory.html )の産業アドバイザーやP-ALMキャピタル株式会社( https://p-almc.com/ )の産業アナリストのお仕事を受けながら、流通・消費を中心とした調査研究を行っております。2024年5月で退任しましたが、アークランズ株式会社の社外取締役・監査等委員・指名報酬委員も経験させていただきました。
[補足2 「知見ラボ」と「風待食堂」について]
- 証券アナリストでお世話になったIRや財務、経営企画の方々と気楽な呑み会を行っておりましたが、2020年のコロナ禍で直接お目にかかることが難しくなり、当時流行った「ZOOM呑み会」を始めました。ただ、画面を通して呑んでいるのもつまらなかろうということで、今後何かするためのビークルとして「知見ラボ」を設立し、このホームページを立ち上げました。そこに各自の好きなブログを各コーナーを設けました。
- わたくしのコーナーは「風待食堂」というちょっと妙な名前ですが、これは高倉健さん、倍賞千恵子さんなどが出演された名画「益~STATION~」の舞台となる、北海道増毛町の実在の食堂の名前です。
- なかなか思うように進まない人生、思い出深きふるさと北海道、そしてそれを象徴するような八代亜紀さんが唄う「舟唄」に感動し、このタイトルとしました。「知見ラボ」の仲間である竹垣さん、吉岡さんという先輩が「うまく行かないときには風を待つ時間をもつことも重要」と仰ってくれたこともこのタイトルとした理由です。
- お世話になった方々にメールで送るパターンと、「知見ラボ」のコーナー( https://www.chikenlab.net/?cat=15 )に過去分を含めてアーカイブしております。基本的に内容は、流通・消費や社会全般で思うことをつらつらと書いております。その内容の稚拙さ、および長い間書き綴ってきたため、既に内容や社会との認識に齟齬があることはご容赦ください。
