- 25年間くらい前から赤羽駅の近くの飲み屋で、不定例呑み会を友人とやっている。東京都から埼玉県に利根川を渡る東京側の最後の駅である「赤羽駅」はかなり大きな駅で、調べると「東北本線」、「宇都宮線」、「高崎線」、「上野東京ライン」、「湘南新宿ライン」、「京浜東北・根岸線」、「埼京線」が停車することに加え、停車はしないが「東北新幹線」「上越新幹線」、「北陸新幹線」「山形新幹線」、「秋田新幹線」といった新幹線も通過する、鉄ヲタ垂涎の駅だ。


- と同時に赤羽は「せんべろ」の聖地でもある。「せんべろ」とは「千円でべろべろに酔える店」の略で、デフレ下で生まれた比較的新しい言葉だが、要するに駅周辺に割安でお得な呑み屋が多い。そして、かなり多くの店が昼や、場合によっては朝からやっている。これには理由があり、利根川沿いで、なおかつ埼玉県への入り口である赤羽には多くの企業の工場や営業所などがあるからだ。その多くは「高度経済成長」時代には日勤だけでなく、夜勤もあり、その夜勤明けの人たちが家に帰る前に一杯やるために朝から開けていると「まるますや」のオバチャンから聞いた。「まるますや」とは、数ある赤羽の中でも有名な呑み屋である。鯉や鰻、すっぽん(!!)といった地元でとれる川魚が信じられないほど安く、一階は止まり木の呑み屋、二階は宴会用の大部屋があるのだが、その二階に上がる急階段には「呑んでいる人はお断り!」という手書きの張り紙が貼ってある。「せんべろ」の聖地の店で「呑んでいる人」も何もなかろうが、要するに飲みすぎて他人に迷惑をかける人はお断りという意味だ。最近、テレビのワイドショーで取り上げられているのを見たら、インバウンドの方が多くいらしていて吃驚した。




- 赤羽に集う友人の共通点は、ほぼ全員がGMS(総合スーパー)の社員と証券アナリストなどのマーケット関係者だったことだ。また、地方のスーパー経営者が上京した時は、「歓迎会」と称して会を開いては実によく呑んだ。なぜ赤羽かといえば、勘の良い人は気づく通り、赤羽には西友の本社があったからである。そのため西友の人は常連であり、いつも予約係をしてくださった。加えて、ダイエーが池袋駅からほど近い成増に本社があったこともあり、寂しい財布の中身でも十分楽しく飲めることからと、この妙な呑み会は赤羽で開催するようになった。


- ただ、同時に「赤羽」でGMSの人間が酒を酌み交わす象徴的な意味がある。検索してみれば一発でわかるのだが、1970年ころ、人口集積地である赤羽にはダイエー、西友、イトーヨーカ堂、長崎屋のGMS大手が出店し、熾烈なシェア競争を行った地でもある。この「赤羽戦争」と呼ばれた出店競争は激烈をきわめ、その頃の店舗の配置を見ると、どれだけ激しかったかがわかるだろう。ちなみに下の地図には記載されていないが、「すずらん通り」左上にイトーヨーカ堂、長崎屋が出店していた(イトーヨーカ堂は後年、駅の東口再開発に合わせて移転増床)。特にダイエーと西友の競争は激烈を極め、ダイエーがA館とB館に分かれる広大なものを公道に架けられた通路を自由に行き来できるものであったのに対して、西友は二店舗をわずか数十メートル間隔で配置した。この「赤羽戦争」はタレントの壇蜜さんのご主人で漫画家の清野とおるさん(赤羽について多くの著作がある)の漫画にも描かれているので、興味がある方は是非、一読を。


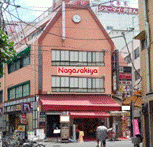

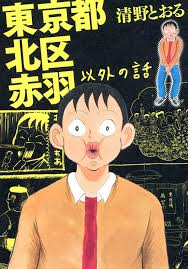

- ただ、コロナ禍のため「まるますや」も毎日盛況だった宴会需要が一気になくなり、今は二階の宴会用大部屋は閉鎖されたままである。そのため、往年は仲間が喧々諤々の議論をした呑み会も、開催できなくなってしまった。まことに残念だ。
- とはいえ、何人かのメンバーは文明の利器、リモート会議システムを使ってバーチャル呑み会をしている。一時期はやった、いわゆる「ZOOM呑み会」だ。ただ、これも数回やると飽きてくる。だから、各人が持ち回りで得意分野のプレゼンとそれを酒の肴にした会へと形を変えた。先日は、筆者が「近年の流通の変化」を語れというお題をいただいたため、人口減少による売上低下リスク、コストアップによる利益率の低迷、そして最近の企業買収や、優良企業中の優良企業であった7&IHDの近況などについてプレゼン&意見交換をした。特に平成バブル崩壊に伴う財務面での苦しさから経営困難に陥った何社かの企業とは違って、百貨店やGMSの事業部門収益悪化、そしてアクティビストにそのことを厳しく批判されたことが変化の原因となった7&IHDについては、どういう考え方があるのかと、その視点・視野について議論が盛り上がった。




- 意見は様々ではあるが、やはり井坂社長への経営バトンタッチから九年間での大きな事業変化、それをもたらしたアクティビストおよびステークホルダー主義の高まりなど、社会の変化というもうひとつの環境変化に話題は集中した。そんな中、筆者を含む多くの友人は、「今回の7&IHDの大きな経営変革を残念」と思う立場だったのだが、それに対して敢然と反論をおっしゃったのが新卒で入った企業が業績悪化から、他の資本の経営へと委ねられた企業での勤務を長く経験した友人であったことには驚いた。
- 彼の意見はこうである。
「我々が属していたGMSにしても、百貨店事業にしても、もう金属疲労を起こしていたことは私たち自身が知っているはず。老兵は消え去るのみ。しかし、日本はそれを良しとせず、もはや収益を十分に上げることのできない『ゾンビ企業』を政財界が生き残らせてきたことが、今の失われた30年という状況を生み出してきた。イトーヨーカ堂が顧客に支持されなくなり、売上も収益も得られなくなったということは、社会に支持されなくなったということだ。流通業の正義は消費者の支持にこそある。その支持を失ったならば、事業から撤退し、そこで浮いた資金で支持を得ているコンビニエンスストアに投資をすべきというアクティビストの理屈にはなんの矛盾もない。どうして、みんながそんなにこの件を寂しがるのか自分にはわからない。自分が人生の多くをかけた企業が、マスメディアや世間に『ゾンビ企業』と揶揄されたことを考えると、消費者の支持を失った流通業は黙って市場を去るべきだ。」
- 根っからの関西人で、そのジョークや広範な分野での博識さにはみなが感心し、リタイヤ後は大学で学び直しをしている彼の日ごろの面白おかしい語り口と180度違うこの言葉には友人一同考えさせられた。「一所懸命働いて、務めてきた会社が破綻して、それで必死に色々なところで生き残ってきた60代の人間が、ノスタルジーに浸ってどないするんや。それこそ老害やで。」と付け足した言葉には重みがあった。
- これまでもしばしば触れたように、筆者は「貪欲な資本主義」や「アクティビスト」、そしてそれを支える「ポリティカルコレクトネス」には良い感情は持っていない。しかし、友人の発言はそれを踏まえて、である。なんであろうと、借りたカネは元利ともにきっちり返さねばならないし、顧客(=消費者)や株主や銀行からの信頼には応えられないのでは事業をする意味がない。それを強い口調で語る友人が、債務不履行などを一度も起こさず歯を食いしばってきたにもかかわらず、『ゾンビ企業』とさんざんマスメディアに揶揄され、とても悔しい思いをした企業で活躍した方であったことは、まことに重く、深い意味があった。
- 2025年4月中旬頃から、トランプ氏によるいわゆる「トランプ関税」が話題をよんでいる。これを執筆している時点では、マスメディアのニュース番組はトランプ氏や「トランプ関税」の根拠を袋叩きだ。確かに「トランプ関税」は驚くような内容ではある。しかし、経済や産業は、いつも平穏無事な世界の中で進むわけではない。投資家の中には「投機」を目的とする者も包含されるし、国や企業同士の駆け引きはしばしば理不尽に映るものがある。しかし、それを「純粋まっすぐ君」で批判しても始まらない。どうすれば、その理不尽な要求を多大のwin-winに変えていけるのか知恵を絞ること、それがビジネスの醍醐味でもある。7&IHDでのアクティビストや買収を試みる人々に対してどういう感情を抱くかは勝手だ。しかし、それが法を犯していない限り、文句を言われる筋合いはないことも法治国家のルールである。「ここのままではわしら、みんな、老害やで」と締めくくった友人の言葉は、ちょっと「あまちゃん」になっていた筆者の心に刺さった。
(了)
