- 週に一回、このコラムを書く度に筆者が悩むのは「これ、おっさん臭い思い出話、書いてるだけじゃないか?」だ。もうすぐ62歳になる自分にとって、これからの人生よりも、これまでの人生の方が長かったのは厳然たる事実。仕方ないとは思うけど、経験知に基づいたことにどうしても内容が偏る。。。という予防線、前振り、言い訳をして今号も書き始めよう。ジョブズも言っているじゃ無いか「点(ドット)を打ち続けろ。事前には分からずとも、事後にはその意味が繋がる」と。「それを信じて生きろ」と( https://www.youtube.com/watch?v=XsRpvWHIVw0&t=500s )。まぁ、もっともそれはなかなかしんどいことではあるけれど。

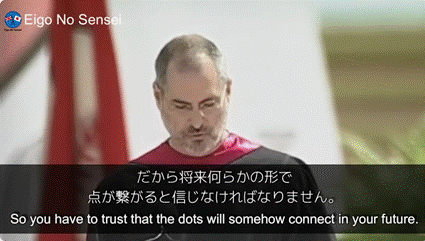
- その世代にとっての「ヒーロー」というのは必ずいる。これを読んでくださる方にも多くのヒーローがいるだろう。一人を挙げろと言われると難しいが、ふと何かのおりに思い出すのは、筆者にとってはミュージシャンの矢沢永吉さんだ。リーゼントで頭を固めた矢沢さんに、ちょっとヤンチャなファンが「 E.Yazawa 」と書かれたタオルを曲に合わせて投げるという、有名なライブ、コンサートの絵図と違って、彼が歩んできた人生は「地味」「地道」という一言に収斂される。「成りあがり」という1978年に発売された彼の最初の自伝は、華やかに見える彼のステージやライブとは裏腹に、リーゼントを固める整髪料を落として、近くの銭湯に子供を連れて通う普通の「オトーサン」である自分のことが書かれている。そして彼は言う。「カネがなければ、自分の本意じゃないことをしなければならなくなる。カネ大事。だからヤザワ、ライブ終わったら家に帰って、メシ食って、子供を銭湯に連れて行きますよ」と。15歳の筆者は華やかな彼とその地道な生き方をしている彼のギャップに衝撃を受けたことに衝撃を受けた。



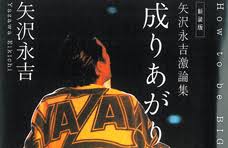
- いまはBS放送もあるが、以前はNHKのテレビ放送は「総合テレビ(今のG)」と「教育テレビ(今のE)」の二つだった。「教育テレビ」は非常に画期的なチャンネルで1959年に始まった「世界で初めての教育専門チャンネル」だ。「米百俵」に代表される、後進のための教育を大切にする日本文化を代表する世界に誇る放送チャンネルである。そして、当初は学校教育の副教材に加え、幅広い年代層への趣味教育番組(「きょうの料理」「趣味悠々」)、どっしりしたドキュメンタリー(「ETV特集」)などに加え、土曜日の21時台から放送されていた「若い広場」は、あまたの週末ゴールデンタイム番組が民放でしのぎを削る中で、しっかりとした内容で強い支持をうけた番組だ。後の「YOU」という大友克洋さんのタイトル画と坂本龍一さんのテーマ曲に乗って始まる軽妙な番組に姿は変えたが、その中身は糸井重里さんや日比野克彦さんというサブカルチャーの代表選手がYMO、ビートたけし、忌野清志郎、アントニオ猪木などを招き、視聴者に剛速球を投げかける、迫力の番組だっった

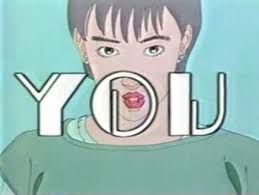

- この「若い広場」は、そのタイトルからは想像もできないラジカルな内容をしばしば流した。テレビというマスメディアには迎合しないアーティストに真っ正面から取り組んだのが「矢沢永吉からのメッセージ」(1980年)や「オフコースの世界」(1982年)だ。特に前者はほぼ全編、ライターの中部博によるインタビューで、矢沢が語る内容のヘビーさに若き視聴者は黙り込んだ。
・「いつの時代だって、今イージーになっているって言うけど、やつ奴はやるのよ。やらない奴はやらない。僕ね、この前言ったのね。いいんじゃない、やる奴はやるから、やらない奴はいくららフォローしてもケアしてもやらないと僕は思ってますから。(でもそのうち)凄い奴出ますよ。今、また出てきますよ、凄いのが。そいつが出たその後にも、また凄いのも出てくる。だから、アナタも(やらない奴ではなく)そのやる奴の部類にはいったら?、ってそう言いたいのね。( https://youtu.be/WijWrispbrM?si=JVWoV51UVZ3Soydb )」
・「5のプラスをチャレンジしようと思ったら、絶対にマイナスの5が背中合わせにつきまとっているといっても、言いすぎじゃ無いんだ世の中は。そして10望もうと思ったら、10の敵がいる。。。そうだなあ、男として力を発揮できるのは、あと30年くらいしかないんだ。オジンになったら、みんな隠居だしね。30年、だったらやりましょうよ、泣いても笑っても30年しかないんだから、あとは死ぬだけよと思ったら、僕はプラスの10を取ろうと思ったね。( https://youtu.be/wFD9E_aFrbI?si=yq1BZvzmm_txnYuR )。」
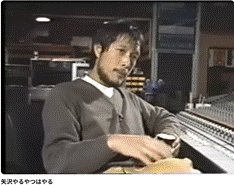

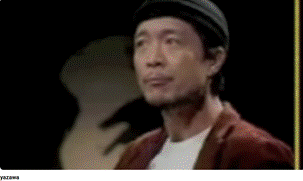
- 「やる奴ぁやる、やらない奴ぁやらない」、この言葉は衝撃的だ。しかも話しているのは広島の貧乏のどん底から這い上がった30歳の大スター。そして今、筆者は最近こんなネット記事を読んで、同じように衝撃を受けた。東日本大震災で傷ついた心を鼓舞してくれた「なでしこジャパン」の主要メンバーもまた、ここまで苦しんでいたのか、と。
・(前編) (元なでしこ・宮間あやさん(40)「絶望でしかなかった。でも生きていくと決めた…」。彼女が初めて語った《引退の真相》とサッカーへの思い(東洋経済オンライン)https://toyokeizai.net/articles/-/880805
・(後編) 元なでしこ・宮間あやさん(40)突然の引退から9年。「大切なものを守るために、自分はどうなってでもがんばりたい」表舞台に戻ってきた理由(東洋経済オンライン) https://toyokeizai.net/articles/-/880806?display=b

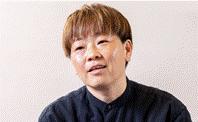
- 色々な企業を訪問し、お話を伺うと、不思議なことに経営者の悩みはある数個のところに収斂する。それは以前にも書いた「悪意無き組織と人材資源の劣化」だ。人口減少がさらに加速し、派遣労働解禁や働き方改革という美辞麗句をつけられた労働環境の変化は、「人をスポイル」している。それを誰かが意図してやっているのかどうかまではわからない。ただ、「熱い想い」をもつことはカッコ悪いことと見なされるようになってきていることは事実だ。そして、そういう時代は今回が初めてではない。太平洋戦争後の高度経済成長が終わり、オイルショックが来る直前の1970年代安保ブームが終わった頃、若者は「私たち」であることをすて「私という個」に戻っていった。「三無主義」(無気力、無関心、無責任)と彼らは呼ばれ、その次の1980年代は「しらけ世代」と呼ばれ、「熱いことが恥ずかしいこと」であるように扱われ、メディアもその潮流に乗った。そんな頃に語られたのが矢沢永吉さんのインタビューであり、そして今の時代に語られたのが「なげしこジャパン」の宮間あやさんの記事だ。
- そしてそういう風潮に悩んでいるのは管理職も同じだ。「熱量の低さ、しかし、その熱量を上げるためにアクションをすれば、それはハラスメントとみなされ、自分の地位が危うくなるジレンマ」、その立ち位置に悩む経営者や管理職がごまんといる。そして筆者は懸念する、「それがこの国を滅ぼす、巧妙に設置された時限爆弾なのではないか」と。「やつ奴ぁやる、やらない奴ぁやらない」、どうせならばいつまでも「やる奴」でいたいと思うのは昭和世代(最近のこういうカテゴライズも実はキライだ)のノスタルジーだとは筆者は思ってはいない。
(了)
