- 風邪を引いたらしい。まだ残暑で暑く、おまけにゲリラ豪雨で湿度も高い中、熱さ対策と除湿のためにエアコンをつけているのに、体が冷えるのでタオルケットをかぶって布団で寝ている姿は、我ながらマヌケだと思う。しかも、「寝るのにも体力がいる」年齢になったので容易に眠れない。仕方ないので無理矢理目をつぶって、昔から今にいたることを脈絡も無く思いだしたりする。世は三連休だし、ま、いっか、なんて言い訳をして。
- それにしても北国の田舎の小学生が、なんで、ここ大東京の片隅で風邪引いて床で寝てるのかなと振り返ると、それはそれでなかなか面白い。暇に飽かして、「俺、何がしたかったんだっけ」とぼんやり考えていると、「おお、それ、すげえ!」と思う「ノリ」が好きだった「だけ」なんだなと、その浅薄さに笑う。特に「すげえ!」の中でも、一般に考えられていることと実態が違うことを見つけた時が一番楽しくて、いまでもその仕事をしている。つまりは「ギャップ萌え」だ。考えて見れば、証券アナリストなんて、「ギャップ」を探すことが商売だ。1)予想されている業績よりも上振れする(上方修正)・下振れする(下方修正)、2)まだ株式市場では知られていない凄い企業を見つけた、などの時は一番「萌える」。だってアナリストレポートに必ず書くのは「サプライズあり」「サプライズなし」だもの。そして、そのサプライズ「萌え」を誰かに話したくってしょうがなくなる。ただ、聞き手の相手が「はいはい、今日は何ですか?」とあまり興味を持ってくれない、それもアイドルの「萌え」に似ている。そうか、やはり自分もヲタクであったか、そんなことを考える。
- 有り難いのは、今もまだまだ萌える「ギャップ」がほうぼうに転がっていることだ。先日、ある企業を訪問した。世間ではIT・DX系、システム系と言われている企業だ。消費・流通を領域としている自分では理解できないのでは?と思いながらも、前に在籍していた会社の先輩のお誘いでもあるので、不安を抱えながら有り難く同行させていただく。ところが、経営者のお話を聞くとどんどん魅了されている自分がいた。最初はIT・DX系ということで怯えつつ静かにお話伺っていたはずなのに、しまいには「よく喋りますね(苦笑)」と先方から言われ、当方が頭をかく事態に。それは世間の「IT、DX系の企業」というラベルと、経営者が目指している実態の差に「ギャップ萌え」したからだ。
- その企業はSNSを分析し、小さいながらも注目を浴びている流行やトレンドを抽出するのが得意だ。なるほど、これは確かにIT、DX系だ。ところが経営者の方が言うには、「もう成熟したと思った産業分野にも、そういう密かに伸びているテーマはたくさんあるんですよ。そこから次に注目を浴びるものをビジネスにするのが当社の仕事です」と仰った。おぉ、それはもはやIT、DX系企業ではなく、マーケティング企業ではないか。事実、その企業の決算説明資料には「ニッチトップ狙うマーケティング会社です」としっかり描いてあるのだが、先入観は怖ろしい。市場参加者はほぼ全員がこの企業はIT・DX系のシステム企業だと思い込んでいる。ネット上で誰もが観ることができる決算説明会資料にはこんな表が掲載されているのに、だ。
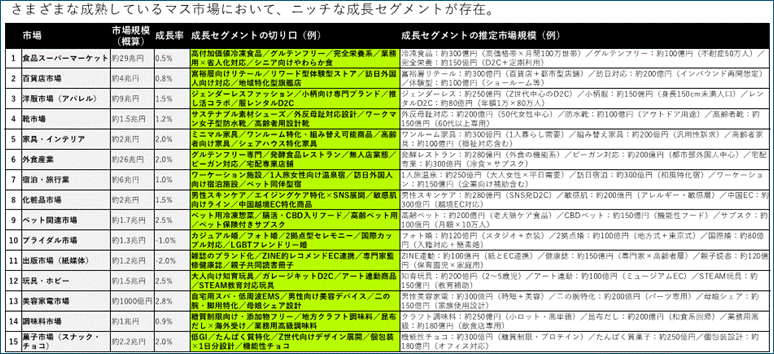
- 筆者はこれを拝見して、思わず「むぅぅ~~」と唸った。「字が小さい=情報が詰め込まれている」ので読みにくいかもしれないが、それぞれの「成熟産業」に、どういった成長余地のある「ニッチ市場」があるかをまとめた一覧だ。しかもご丁寧に、緑部分でハイライトしている「ニッチ市場」だけでなく、それらが、どれだけの潜在マーケットがあるかが右側に試算してある。いや、これ、電通総研か博報堂生活研究所に有料で依頼する内容でしょ。どの項目も「なるほど」と思うことばかりなのだが、例えば食品スーパーマーケットならば「グルテンフリー(食材)」「シニア向けやわらか食」、宿泊旅行業ならば「ペット同伴型宿」、ブライダル市場では「LGBTフレンドリー婚」などと記載されている。
- もしかすると、ここまで読まれた読者は「ははーん、まぁ、あるあるだよね。でも、別に目新しくないんじゃない?」と醒めたコメントをするかもしれない。しかし、重要なのは、1)これがSNSという膨大な生活者の声から「濾しとられた」データであること(=エビデンス)、2)右側の試算にあるように結構な規模の試乗試算市場がある(=マネタリーに落とし込んでいる)、ことだ。「ははーん、あるあるだよね」と思っても、それをビジネスに取り込めるというバックデータと市場規模試算があるとないでは全く意味合いが違う。前者は単なる思いつきだが、後者は事業計画を組める。筆者の「ギャップ萌え」マインドが震えた。
- 同時に考えさせられるのが、そんな貴重なデータが膨大な決算説明資料に埋もれていることだ。2025年4月段階での日本の上場会社数は3,946社である。全部の企業がこうした決算説明資料をWebに掲載していないにしても、決算説明会を行っている企業は85.4%が年に二回決算説明会を実施している(出所:日本IR協議会「2025年 IR活動の実態調査」)。とすれば、3,370社は決算短信や有価証券報告書と別に決算説明会資料を出しているということだ。
- じゃあ、それをすべてチェックしている人間はいるのか?、AIを使ってもいいから全社チェックした経験があるヒトや機関はあるのか?。私見だが、多分NOだろう。仮にAI使って調べるにしても、プロンプトになんと入力すればいいか、これは極めて難しい。ということは、「隠れた宝物を探し出すチャンス」はまだまだ豊富に残っているといううことだ。まさしく「灯台もと暗し」。よく眼鏡を額の上にあげておいて、「私の眼鏡はどこ?」と探すギャグがあるが、実はおんなじことを私たちもしているのかもしれない。それは反省でもあり、同時に、チャンスがまだまだ残っているということでもある。
- あかん、風邪でまた微熱が出てきた。本日はここまで。図表一枚の愛想無しのコラムとなりましたが、ご容赦を。ただ、「ギャップ萌え」も「灯台もと暗し」の宝探しも結局は手と足と頭を動かさないと見つからないし、一方でどうやらそういう宝物は足下にゴロゴロ転がっているらしい。なお、上記の図表はどこの公表決算資料かは敢えて述べない。三連休の宝探しゲームとして、チャレンジしてみてほしい。
(了)
